インターネットが情報共有のフラット化を推進し、学者、政治家から既存メディアまであらゆる権威を相対化する中、情報や言説の質や真正さを担保するメカニズムもなくなり、フェイクニュースやポストトゥルースが社会にあふれ、エコーチェンバーやフィルターバブルが、都合の良い言説だけを信奉し合う心地よい閉鎖空間に人々を閉じ込めている。この危険な状況で、人間は感情的、近視眼的、浅薄な極めて短い文章しか読まなく、いや、読めなくなってきている。(駒場東邦の国語科の先生との対談でも同じ話題となった)
国語の授業を通して、今年も「良質な」「長い」文章を子供と一緒に読んでいきたい。そして、その延長線上に、同志でもある私学の国語科の先生方(知り合いも実に多い)が作問する入試問題が解ける生徒が育成できると確信している。
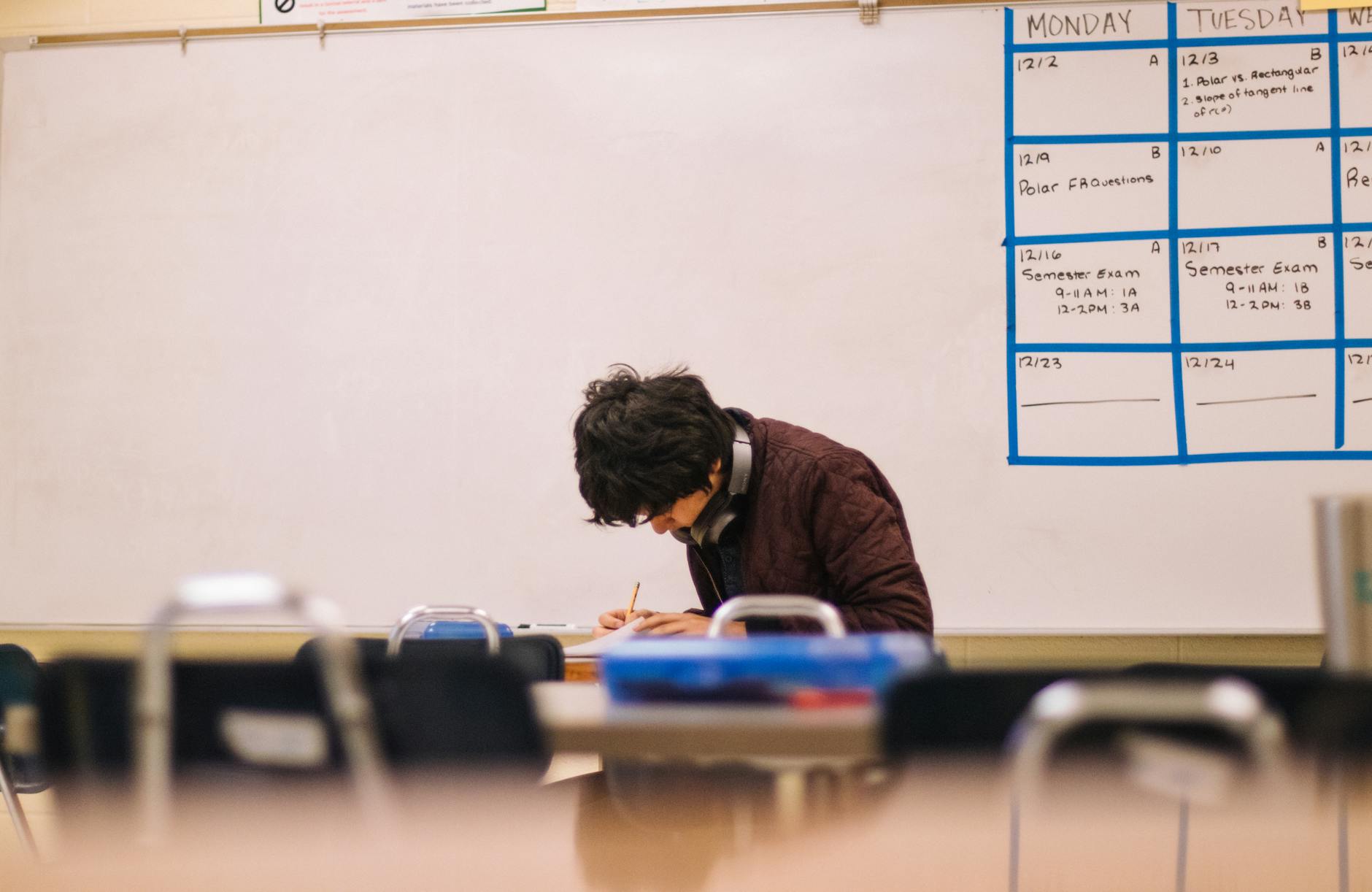

 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス